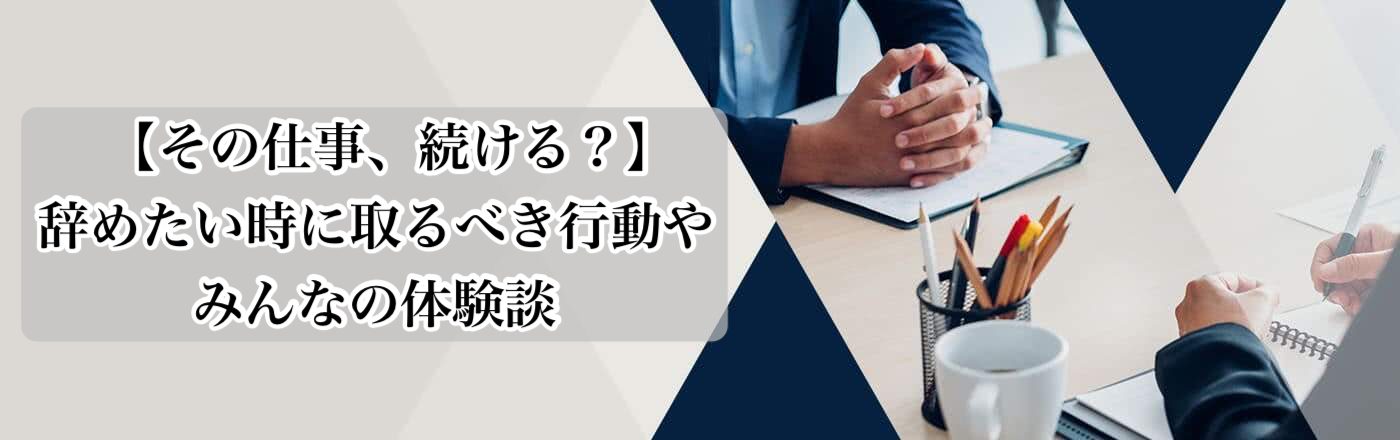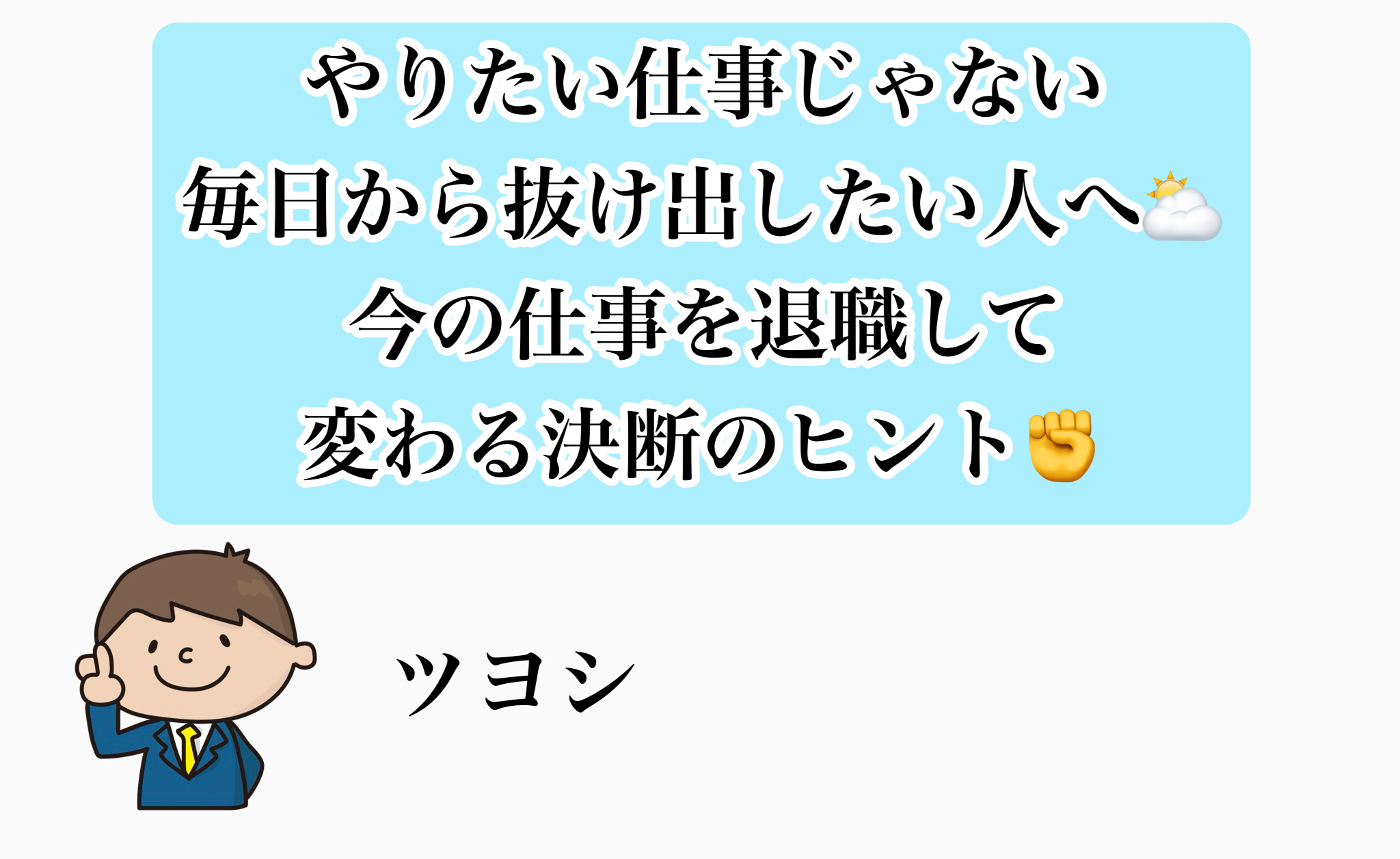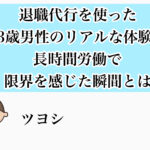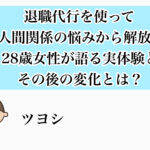「この仕事、なんか違うかも…」そんな気持ちを抱えながら働いている方、きっと少なくないですよね。
やりたいことが分からないまま就職して、気がついたら何年も経っていた。
なんとなく働き続けているけど、心のどこかでずっとモヤモヤしている。
そんな日々が続くと、「自分って何のために働いてるんだろう」って思う瞬間が出てきてしまいます。
実際、「自分のやりたい仕事ではない」という理由で悩んでいる人はかなり多いです。
たとえば、マイナビの転職調査では「現職に不満を感じる理由」として、「やりがいのなさ」や「仕事内容が合っていない」といった回答が上位に入っていました(出典:マイナビ転職動向調査2023)📊。
さらに「向いてない仕事 辞めたい」「やりたい仕事 分からない」といった検索ワードも、毎月何万回とGoogleで調べられているというデータもあります(出典:Googleキーワードプランナー)。
つまり、やりたい仕事が見つからないまま働き続けている人は、あなただけじゃないということです。
そこで今回は、今の仕事は自分のやりたいことではないと感じている場合、どんな選択肢があるのか、どうやって次の一歩を踏み出せばいいのかをお伝えしていきます。

納得できる働き方を見つけるための第一歩として、この記事が少しでもあなたの気持ちを軽くできたら嬉しいです🌿
今の仕事が「やりたいこと」じゃないと感じる根本的な理由とは?
実は、今の仕事に対して違和感を抱く理由には、はっきりとした“構造”があります。
ここを理解しておかないと、次に転職したとしてもまた同じ壁にぶつかってしまう可能性があるんです。

ここでは、「今の仕事はやりたいことじゃない」と感じてしまう、根本的な4つの原因を丁寧に掘り下げていきます!
向いてない仕事を続けていると違和感が強まる
仕事って、どれだけ給料が良くても、自分の性格や価値観とズレていると本当にキツくなってきます。
例えば、人と話すのが苦手なのに接客業をしていたり、細かい作業が苦手なのに事務職に就いていたりすると、毎日が「修行」みたいになってしまいますよね。
リクナビNEXTの「グッドポイント診断」などを使って自己分析してみると、「自分に向いている働き方」って意外と具体的に見えてきます。
そういう情報を知らずに職場を選んでしまうと、「なぜか仕事がしんどい」という状態にハマりがちです。
向いてない仕事を無理に続けていると、自信をなくしたり、自分の可能性を否定してしまったり、どんどんネガティブになってしまいます。

違和感が強くなるのは、あなたの感受性が高いからではなく、「ちゃんと自分を理解しているから」なんです。
「やりたいことが分からない」まま選んだ就職の影響
特に新卒で就職した人の多くが、「本当にやりたい仕事なんて分からないまま就活を終えた」という経験をしています。
「なんとなく内定をもらったから」「周囲が褒めてくれたから」そんな理由で選んだ会社に入ったものの、数年経ってから「この仕事、心から好きじゃないかも」と気づくパターンって本当に多いです。
実際、マイナビの調査でも「入社後3年以内に転職を考えたことがある」人は全体の6割以上というデータが出ています(出典:マイナビ転職動向調査2023)。
その理由のひとつが、「やりたい仕事かどうかを深く考えずに選んでしまったから」という回答です。
つまり、やりたいことが分からないまま仕事を始めた人ほど、「なんか違うかも」と後から気づきやすいという構造があります。
でも、それは全然恥ずかしいことじゃないです。

むしろ、今からちゃんと見直すチャンスなんですよ。
周囲の期待や安定志向が判断を狂わせる原因
「親が喜ぶから大手企業に入った」「友達に自慢できるから公務員になった」そんなふうに、自分以外の誰かの期待を軸にして進路を選んだ経験って、ありませんか?
もちろん、安定した職場に就くことは悪いことじゃないです。
でも、「他人の価値観」で選んだ道は、あとから自分の気持ちとズレが出てきやすいです。安定してるけど満足してない。
評価されてるけど楽しくない。
そんな状況って、長くは続きにくいんです。
特に日本では「安定=正義」みたいな風潮が強くて、転職やキャリアチェンジをネガティブに捉えられることもありますよね。
でも、他人の人生を生きても、自分の心は納得しない。

そんなシンプルな事実に、ふと気づく瞬間があるんです。
社風・上司・評価制度など“価値観のズレ”が苦しさを加速させる
仕事内容そのものには興味があっても、「会社の雰囲気が合わない」「上司の考え方が古すぎる」「何を頑張っても評価されない」こういった“価値観のズレ”がストレスになっているケースもよくあります。
例えば、チャレンジ精神がある人が、年功序列で変化を嫌う会社に入ると、どれだけ頑張っても正当に評価されないと感じてしまいます。
また、自由な働き方を望む人が、細かすぎるルールや管理が厳しい社風に入ると、息苦しさを感じやすいです。
転職サイト「OpenWork」などの企業口コミを見ていても、「仕事内容よりも社風や評価制度が合わない」という退職理由がたくさん出てきます。
つまり、どれだけ仕事内容が魅力的でも、それを取り巻く環境が合わなければ、結果的に“やりたい仕事ではない”と感じてしまうんです。
このように、今の仕事に違和感を持つのは、ただの感情論ではなく、ちゃんとした理由があります。
「こんなはずじゃなかった」と感じるのは、むしろ自然な反応なんです。

だからこそ、自分の違和感を「甘え」と切り捨てず、「何がズレているのか」を冷静に見つめ直すところから始めてみて下さいね🌱
やりたくない仕事を続けると起こる3つのメンタルリスク
「今の仕事、本当はやりたくないけど…」「でも辞めるのはまだ早いかも」そんなふうに気持ちをごまかしながら働き続けている方、多いと思います。
でも実は、その“なんとなく”の違和感を放置していると、思っている以上に心にダメージが蓄積してしまうんです。
ここでは、やりたくない仕事を続けた先にどんなメンタルのリスクが待っているのかを、3つの具体的なケースに分けてお伝えします。

どれも実際によくある話なので、「これ自分かも…」と思ったら、早めに対処を考えてほしいです!
毎朝の出勤がストレスになり身体に症状が出る
朝目覚めた瞬間に「また今日も行かなきゃ…」と重たい気持ちになる。
出勤前になるとお腹が痛くなる。
会社に向かう電車の中で頭痛がしてくる。
こういった症状、決してレアではありません。
むしろ、長期間やりたくない仕事を我慢し続けている人にとっては、よくあるサインです。
これは“仮病”ではなく、ストレスによって自律神経が乱れている証拠です。
厚生労働省のデータでも、長時間の我慢や精神的な負荷が、胃痛・頭痛・不眠などの身体症状として現れることが報告されています(参考:厚労省「働く人のメンタルヘルス」)。
最初は週に1回だった体調不良が、いつの間にか毎日に変わっていく。
そうなる前に、「これはおかしい」と自分で気づいてあげることがすごく大切です。

身体が出しているSOSは、ちゃんと意味があります。
自信喪失・無気力・慢性的な疲労に襲われる
「やりたくない仕事をしているだけなのに、どうしてこんなに疲れるんだろう…」というのは、“作業疲れ”じゃなくて、“気持ちのエネルギー”が消耗しているサインかもしれません。
興味のない業務、納得できない目標、やりがいのない日々。
それが続くと、自然と脳も「この仕事に意味なんてない」と判断して、やる気が出なくなってきます。
そして、どれだけ頑張っても評価されなかったり、やりたくないことを延々と繰り返したりしていると、「自分って本当にダメかも」と思ってしまうようになるんです。
その結果、自信がなくなっていき、何に対しても「どうせ自分には無理」と思い込むようになってしまう。
これがいわゆる“学習性無力感”という状態で、メンタル不調の入り口とも言われています(出典:心理学者マーティン・セリグマンの研究)。
やる気が出ないのはサボりじゃありません。

心が疲れてしまったからなんです。
転職に動けないまま、時間だけが過ぎていく現実
「辞めたいけど、何がしたいか分からない」「辞めたら生活が不安」と思いながらズルズル続けてしまうと、気がついたら1年、2年…と時間が過ぎていた。
そんな声、キャリアカウンセラーの現場でも本当によく聞きます。
やりたいことが曖昧なまま働いていると、次の選択に踏み出すための“軸”が見つからなくて、どんどん動けなくなってしまうんです。
そしてそのうち、「年齢的にもう遅いかも」「職歴が中途半端で不利かも」と、自分に言い訳をし始めてしまう。
でも、これって本当にもったいない状態です。時間は有限なのに、自分の気持ちにフタをしたまま流されるように働き続けることほど、消耗が激しい働き方はありません。
転職が正解かどうかは人それぞれですが、「何もせずに我慢する」ことだけは、避けた方がいいんです。
やりたくない仕事を続けると、心と身体の両方がジワジワと蝕まれていきます。
そして厄介なのは、それに慣れてしまうこと。
「こんなもんか」と思ってしまうことが、一番危ないんです。
だからこそ、自分の違和感に気づけた今がタイミングです。

ここから先は、「じゃあどうすればいいのか?」を一緒に考えていきましょう。
➡️ 詳しくはこちら
「やりたいことが分からない」状態から抜け出す考え方と行動
「やりたい仕事が見つからない…」って、誰もが一度は通る悩みです。
「とりあえずこの会社に入ったけど、これが本当に自分のやりたいことなのか分からない」「転職したいけど、何がしたいかハッキリしない」
そんな状態にいると、動きたくても動けませんな、それは“考え方”と“行動の順番”をちょっと変えるだけで、スッと道が開けることも多いです。

ここでは、「やりたいことが分からない」状態から一歩抜け出すために効果的な考え方と具体的な行動を、順番にご紹介していきます。
まず「やりたくないこと」から整理するのが効果的
「やりたいことを探す」って、すごく難しく感じますよね。
だからこそ、逆から考える方が圧倒的にラクなんです。
つまり、「やりたくないこと」をリストアップする、というアプローチです。
例えば、
-
接客業は向いてない
-
長時間労働は絶対ムリ
-
チームプレーよりも1人で黙々と作業したい
-
評価が曖昧な仕事はやる気が出ない
こんなふうに、「これはもうこりごり」と思っていることを可視化していくと、自分が大事にしている価値観や理想の働き方が浮かび上がってきます。
これはキャリアカウンセラーの現場でも定番の手法で、「キャリアの棚卸し」として企業の面接対策でも活用されています。

いきなり“理想の仕事”を探すより、まずは“絶対イヤな条件”を洗い出すことが、次に進む近道なんです!
自己分析ツール・キャリア診断で客観的に把握する
自分の強みや向いている仕事を客観的に把握するには、無料で使える「自己分析ツール」や「キャリア診断」がとても役に立ちます。
代表的なものとしては、以下のようなサービスがあります。
-
リクナビNEXTのグッドポイント診断
→ 18種類の強みから、あなたに合った5つを無料で分析 -
ミイダスのコンピテンシー診断
→ 適性職種、コミュニケーションタイプなどを数値化してくれる -
キャリタス就活の適職診断
→ 性格タイプと仕事の相性を組み合わせて表示
こうしたツールを使うと、自分では気づかなかった強みや、向いている職種の傾向が見えてきます。
「分析」と聞くと難しそうですが、直感的に質問に答えるだけなので、30分もあれば完了するものばかりです。
さらに、これらの診断結果は転職活動でもそのまま自己PRに活用できます。
迷ったらとにかく1つ試してみること。

それだけでも、頭の中が整理されて気持ちが軽くなる感覚を味わえるはずです!
向いている仕事が分からない時は“価値観”から探す
やりたい仕事が見つからない人の多くは、「やる内容」よりも「どんな働き方をしたいか」がまだ明確になっていないことが多いです。
だから、向いてる仕事を探すときは、「価値観」をベースに考えるのがおすすめです。
例えば、
-
自分のペースで働ける自由度を重視したい
-
人の役に立てる実感がほしい
-
明確な成果が数字で見える仕事にやりがいを感じる
-
チームで協力してひとつのプロジェクトを進めるのが好き
こういった“価値観”に合う仕事は、業種や職種を超えて存在しています。
「自由度の高さ」を重視するなら、在宅OKのIT系企業やフリーランス。
「人の役に立ちたい」なら、福祉・教育・医療業界などが候補に入ってきます。
この“価値観ベース”の考え方は、迷ったときの軸になってくれます。

「何がやりたいか」じゃなく「どう働きたいか」から考えてみると、自分に合う選択肢が一気に見えてきますよ!
副業・スキル習得で“試してから選ぶ”選択もあり
やりたいことが分からないなら、頭で悩むより“やってみる”方が早いという場合もあります。
今の時代は、副業やスキル習得のハードルがとても低くなっていて、会社を辞めずにチャレンジすることも可能です。
例えば、
-
ライティングやデザインをクラウドワークスで試してみる
-
SHElikesやストアカなどで興味のある分野を勉強してみる
-
noteやVoicyで自分の発信をしてみる
こうやって“試す→感じる→合うかどうかを見極める”というプロセスを踏めば、思いがけず「これ楽しいかも!」と思えるものに出会えることもあります。
やりたいことは、考えても分からない場合があるからこそ、「試してみる」が正解になることもあるんです。
行動することでしか見えない景色って、必ずあるんですよ。

やりたいことが分からないと感じている時点で、あなたはちゃんと自分の人生に向き合おうとしている証拠です!
➡️ 詳しくはこちら
辞めたいけど不安な人へ:現実的な選択肢と準備すべきこと
「今の仕事、やっぱり辞めたいかも…でも、辞めたらどうなるんだろう」そんなふうに不安で足が止まってしまう方、多いと思います。
頭では「このままじゃダメだ」って分かってるけど、生活のことや家族の反応、次の仕事が見つかるかどうかが気になって、なかなか一歩が踏み出せないですよね。
でも実は、“不安がある状態”こそが、退職を前向きに準備するタイミングなんです。
勢いで辞めてしまうより、冷静に現実的な選択肢を整理しながら進めていけば、退職は怖くありません。

ここでは、「辞めたいけど不安」という状態から抜け出すために必要な準備や考え方を、具体的に紹介していきます。
「辞めてもいい」前提で考えると心がラクになる
まず大前提としてお伝えしたいのが、「辞めてもいい」と思ってOKだということです。
日本社会ではいまだに「石の上にも三年」「続けることが美徳」といった考え方が根強く残っています。
でも、その価値観に縛られすぎて、自分の気持ちを押し殺してしまうのは本末転倒ですよね。
厚生労働省の調査でも、入社3年以内に離職する人は全体の3割以上とされています(出典:新規学卒就職者の離職状況 令和4年版)。
つまり、「辞めること=失敗」ではないという事実を、まずはしっかり認識してほしいです。
「辞めても人生終わりじゃない」「今よりラクになるかも」って思えるだけで、心がグッと軽くなります。

その上で、今後どう動くかを一緒に考えていきましょう。
失業保険・転職活動の並行で焦らない選択ができる
「辞めたいけどお金が不安」という方も多いと思います。
ですが、雇用保険に1年以上加入していれば、条件を満たすことで失業給付を受け取ることができます。これはハローワークで申請でき、最長で90日〜150日(条件により延長あり)ほど支給されます。
しかも、退職前に転職活動を始めておくことで、精神的にも経済的にもかなり余裕が持てるようになります。
最近では在職中の転職が当たり前になっていて、「平日夜や土日にエージェントと面談」という流れが一般的です。
おすすめの転職エージェントは以下の通りです。
-
リクルートエージェント:非公開求人が多く、サポートも手厚い
-
doda:キャリア診断が充実していて初心者にも使いやすい
-
マイナビエージェント:20〜30代向けで丁寧なフォローが魅力

これらを活用することで、「辞めたあとに何しよう」ではなく「次が見えてるから安心して辞められる」という状態を作ることができます。
家族・パートナーへの相談で支えを得ておく
退職に不安を感じる大きな理由のひとつが、「周囲にどう思われるか」ではないでしょうか。
特に家族やパートナーがいる方は、「生活に迷惑かけるかも」と思って、辞めたい気持ちを飲み込んでしまうこともあると思います。
でも、気持ちを共有すると、意外と「そこまでつらかったの?」と理解してくれたり、「今後どうしていくか一緒に考えよう」と支えてくれたりする人も多いです。
大切なのは、「辞めると決めたから話す」のではなく、「今こういう気持ちで悩んでる」と早めに共有することです。

相談のタイミングを早めにとることで、信頼関係も保てますし、経済的な話し合いも現実的に進めやすくなります!
退職の切り出し方・タイミング・引き継ぎ準備のポイント
いざ退職を決めたあとに出てくるのが、「どうやって上司に伝えればいいんだろう…」という悩みです。
結論から言えば、伝えるタイミングと伝え方を整理しておけば大丈夫です。
-
伝えるタイミング:基本的には就業規則に従って、退職の1〜2ヶ月前が目安
-
伝え方:「○○という理由で、退職を考えています。引き継ぎもしっかり行います」と冷静に伝える
-
NG対応:感情的に辞表を叩きつける、無断欠勤からフェードアウト、などは絶対避けるべきです
また、引き継ぎ資料の作成や後任へのフォローをきちんと行うことで、トラブルを防げます。
円満退職は、転職先でもプラスに評価されやすいポイントです。
ちなみに、どうしても自分で退職を言い出せないという方は退職代行サービスという選択肢もあります。
法律的に問題のない範囲で、スムーズに手続きを代行してくれるので、「メンタルが限界」という場合には検討してみても良いかもしれません。
辞めたいけど不安だと感じているなら、それはちゃんと自分と向き合っている証拠です。

無理に決断を急がなくても大丈夫ですが、現実的な準備を少しずつ始めておくだけで、未来は大きく変わっていきます。
転職して「自分に合う仕事」に出会えた人たちの共通点
「今の仕事、やっぱり合ってないかも…」と感じたとき、真っ先に浮かぶのが「転職した方がいいのかな?」という疑問だと思います。
でも、「転職しても同じだったらどうしよう」「未経験の業界に行って通用するのかな」と不安になる方も多いですよね。
ここでは、実際に「やりたいことが分からない」状態から転職を決意し、今では自分に合った働き方を見つけた人たちのリアルな体験や、そこに共通して見られる“考え方の特徴”を紹介します。

「こんな働き方もあるんだ」「こういう視点で選んでいいんだ」と思えるだけでも、次に進む勇気が湧いてくるはずです🌱
転職後にやりがいを感じた人の体験談
ある30代女性の方は、もともと事務職で働いていましたが、ルーティン業務にやりがいを感じられず、「自分はこのまま一生“誰でもできる仕事”をやり続けるのかな…」と疑問を感じていたそうです。
転職活動では、「やりたいことが明確ではないけど、人と関わることは好き」という軸に沿って、未経験からカスタマーサポート職にチャレンジ。
最初は不安だらけだったそうですが、今では「お客様に感謝されるたびに、自分の存在が役立ってると実感できる」と話してくれました。
やりがいを感じられるようになった一番の理由は、「誰かの役に立っている感覚」が得られるようになったこと。

仕事内容そのものではなく、“自分が大切にしたい感情”を軸に動いたのがポイントでした。
自分らしく働くために選んだ業種・職種のリアル
また、IT企業のエンジニアから、自然食品店の店長に転職した40代男性のケースも印象的です。
「収入は減ったけど、毎日が楽しい」と語る彼は、「自分は都会のデスクで数字とにらめっこするより、目の前のお客様と会話する方が向いていた」と振り返っています。
働き方の満足度は、年収や会社規模だけで決まるものではありません。
「自分らしい」と思える仕事を選ぶことで、日々の疲れ方も、仕事終わりの充実感もガラッと変わるんです。

彼の場合は、キャリアアドバイザーとの面談で「自然や人とのつながりが好き」という価値観を言語化できたのが、転職の大きなきっかけになったそうです。
未経験からチャレンジして人生が変わったケース
「未経験だから無理」と諦めてしまう方も多いですが、実際は未経験からの転職で人生をガラッと変えた人もたくさんいます。
例えば、営業職からWebデザイナーへと転職した20代女性は、平日の夜や休日にデザインスクールに通いながらスキルを身につけ、ポートフォリオを作って求人に応募。
最初は小さな会社に入りましたが、「自分で作ったもので人が喜んでくれる仕事って、こんなに楽しいんだ」と語ってくれました。
未経験OKの求人は想像以上に多く、特にIT・Web系や介護・保育・販売・物流業界では研修制度が整っている企業も増えています。

「興味はあるけど経験がない」という方こそ、今の時代なら十分に可能性があります。
転職=後悔ではなく“納得”だった人たちの声
多くの人が「転職=失敗するリスクが高い」と感じている一方で、実際に転職した人たちの多くは「もっと早く辞めればよかった」と感じていることがデータにも現れています。
dodaの転職者調査によると、転職後に「満足している」と回答した人は全体の74%(出典:doda転職者白書2022)。
特に、「自分に合う仕事に出会えた」「人間関係が改善された」「スキルアップできた」といった声が多く見られました。
つまり、転職は“博打”ではなく、自分の価値観や条件を整理して選べば、“納得できる働き方”にたどり着ける可能性が高いということです。
後悔しないためには、「自分に合うって何か?」を先に明確にしておくことが大事なんですね。
ここまで紹介してきた人たちは、最初からやりたい仕事が明確だったわけではありません。
むしろ、「今の仕事が違う気がする」という小さな違和感から動き出した人ばかりです。
やりたいことは、ふとした出会いや経験から見つかるもの。

今悩んでいるあなたも、その第一歩を踏み出すことで、“自分に合った働き方”と出会える日がきっとやってきます🌼
おすすめ退職代行サービス
「本当はもう限界…でも、上司に退職の話なんて切り出せない」「辞めたいけど、職場の空気が怖すぎて言い出せない」そんな状況に陥ってしまった方にとって、退職代行サービスは心の負担を減らしてくれる“現実的な選択肢”です。
最近では、ただ辞めさせてくれるだけじゃなく、労働組合や弁護士と提携していて、法的にしっかりとしたサポートをしてくれるサービスも増えています。

ここでは、信頼度・実績・料金面でも安心できる、おすすめの退職代行サービスを2社ご紹介します。
辞めるんです
➡️ 詳しくはこちら
業界でも老舗クラスの知名度を誇るのが「辞めるんです」です。
テレビや雑誌などのメディアにも多数取り上げられていて、累計4万件以上の相談実績を持っています。
-
料金:27,000円(税込・追加費用なし)
-
特徴:即日対応OK・LINEや電話で24時間相談可能
-
対応範囲:全国対応・パート・正社員・派遣などすべてOK
-
強み:実績豊富で信頼感が高い。会社との連絡は一切不要
初めて退職代行を使う方でも、丁寧なLINE対応があるため安心して相談できます。

「言い出せなくて何年も我慢してた」「出勤前に連絡して、その日のうちに辞められた」という口コミも多く見られます!
ニコイチ
➡️ 詳しくはこちら
「もう職場に行けない」「メンタルが限界」という方から絶大な支持を受けているのがニコイチです。
退職代行の先駆けとして19年の実績を持ち、法律や交渉面にも強く、口コミでも高評価が目立ちます。
-
料金:27,000円(税込・追加費用なし)
-
特徴:即日退職・24時間365日対応・電話サポートあり
-
対応範囲:全国対応・正社員・アルバイト・派遣・公務員もOK
-
強み:代行後のアフターフォローが手厚い。書類サポートも万全
他社と比べて「心のケア」にも力を入れていて、退職に関するメンタルサポートまで行ってくれるのが魅力です。
退職完了まで担当者がしっかり伴走してくれるので、不安が大きい方でも安心して任せられます。
どちらのサービスも、「退職の手続きはすべて代行してくれる」「即日対応してくれる」「追加料金なし」という共通点があります。
違いとしては、「辞めるんです」はとにかく実績とスピード重視、「ニコイチ」はサポートの手厚さと心理的ケア重視といった印象です。
「もう明日から行きたくない」「でも、辞めるって言うのが怖い」そんなときは、無理せずプロに頼るのも選択肢のひとつ。
退職代行は、甘えではなく“自分を守るための手段”です。

不安がピークになる前に、こういったサービスの存在を知っておくことで、心に少し余裕が生まれるかもしれませんね🍀
まとめ:やりたいことが曖昧でも、自分の違和感を信じていい
「自分のやりたい仕事じゃない気がする」「このまま今の仕事を続けていて大丈夫なのかな」と、少しでも違和感をがあるなら、その感覚を大切にしてほしいです。
やりたいことがハッキリしていない状態って、すごく不安になりますよね。

でも、それは何も悪いことではなく、むしろ自分の気持ちと向き合おうとしている証拠なんです。
今のモヤモヤを見過ごさないで欲しい
日々の仕事に違和感があるのに、「生活があるから」「もう少し頑張れば変わるかも」と我慢し続けてしまう人は多いです。
でも、その“ちょっとした我慢”が積み重なっていくと、心や体が限界を迎える前に気づけなくなってしまいます。
「なんとなくつらい」「この仕事、ほんとは向いてない気がする」そんな小さなモヤモヤこそ、ちゃんと向き合うべきサインです。
放置すればするほど、気力も体力も削れていきます。
だから今、あなたの中にある違和感を見て見ぬふりしないで下さい。

それがあるということは、「このままじゃいけない」と本能が教えてくれているんです!
辞めること=甘えではなく“選び直す勇気”
仕事を辞めたいと感じると、「逃げなんじゃないか」「甘えてると思われたくない」と不安になりますよね。
でも、続けることだけが正解ではありません。
自分の体調や気持ちを守るために辞める決断をするのは、立派な“選び直し”です。
今の環境に合わなかったからといって、自分の価値が下がるわけではなく、誰かの人生を生きているわけでもありません。
大切なのは、「自分はどう働きたいか」「どんな生き方をしたいか」を軸にして考えることです。

辞める選択はゴールではなく、そこからの再出発。人生は何度でも選び直していいんです。
最初から明確じゃなくても、動き出すことで見える景色がある
「やりたいことが分からない」「向いてる仕事が見つからない」と悩んで動けないときは、完璧な答えを探そうとしないことが大事です。
多くの人が、“やってみて初めて分かる”を繰り返しながら、自分に合う仕事や働き方に出会っています。
まずは「やりたくないこと」を整理する、自分の価値観に気づく、副業やスキル学習で少し動いてみる。
そういう小さな行動の積み重ねが、後から「これだったのかも」と思えるものに繋がるんです。
大きな決断をしなくても大丈夫です。
違和感にフタをせず、少しずつでも動き出すことが、あなたの未来を変えるきっかけになります🌈

やりたいことが見えてなくてもいい。自分の感覚を信じて、今よりもっと納得できる働き方を目指していきましょうね✨